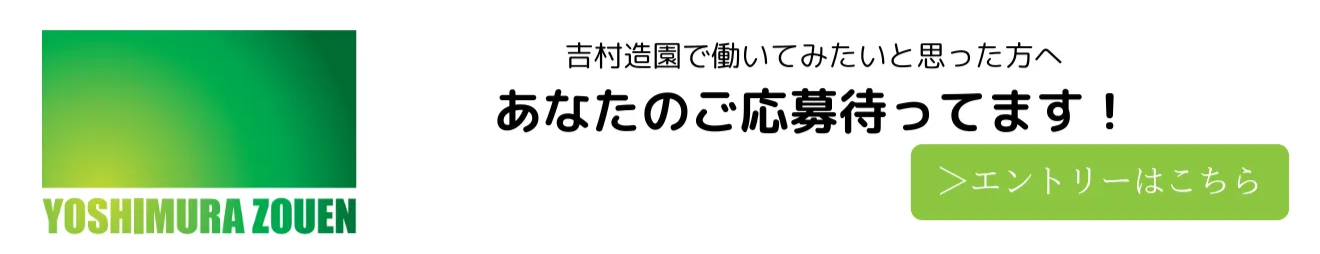現場実況。社長が行く vol.3
奥深き「高木剪定」:未来を見据えた樹形づくり
↓ 動画で見たい方はこちら ↓
「切る」と「残す」の見極めが、木を育てる

結構1年で伸びる量が多いので、毎年やってるような作業。木の形をキープしつつ、良い枝を残していって樹形を良くなるように(剪定する)。
ハサミでも割と太い枝が切れるので。剪定して、全体的に光がしっかり入るように葉っぱの量をだいぶ減らしていって、またこれから切った後また伸びますけど。

1年目でいきなりやるっていうのは、あんまり今はないかな。
でも、そんなに大きくない木とか街路樹とか、分かりやすいのがあれば積極的にやってもらったりする。
Q. この木の高さ(約3メートル)だと、そんなに高くない部類という認識ですか?
うん。これはちょっと低めの高木っていうのかな。

経験と「想像力」が問われる剪定作業
剪定っていうのは、誰がやっても全く同じになるわけじゃないので、人それぞれの感性がある程度出てくる。正解があるようでない…みたいなところがあって。あとはこの木をどういうふうに形を作っていく、時間をかけて。
今、どういう形にするかっていうのも出来るんだけど、3年後、5年後とかにどういう木ぶりにしていくか。どういう形にしていくかっていうのを想像しながらやっていくと、今はここにある枝をいずれはちょっと要らなくなるのかな?とか。ここにあると、あまり木の形が良くならないな…みたいな。
そういう枝をやっぱり今の段階でちょっと抜いていく、外していくみたいな。そういうのが考えられるようになってくると、今のこの状態を綺麗にするっていうことだけじゃなくて、先々、木の形を整えていく。そういうのを意識しながらできるようになっていくっていうのが、上達していくっていうことなのかなと思っているので。
だんだんやっぱり年数が経っていくと、とにかく自分が切った木を1年後に切るとか、2年後に切るとかってなった時に、「こういう風に伸びてるんだ!」っていうのが実感できるシーンが増えてくると、そういう想像力もだんだん出てきたりとか。
そうなってくれば「切るべきところ」あとは「切らないっていう選択肢」とか。そういうの(判断力)がいろいろ深まってくる。そうしてくると、総合的に剪定ができる人っていう風になってくるのかな。

木の個性を活かす剪定の「面白さ」
こうやって切らなきゃいけないっていうよりは、すごい想像力を働かせて「こういう木になっていって欲しい」とか、目的とかを持てると切るべきところが見えてくるのが、選定。なんかちょっと特殊な目的によって正解が違ってくる。
そういう作業なので、またそれが面白いところかなーっていう気がしますね。
あと木によってもね、だいぶ違うし。
自然な樹形を再現する
こういうちょっと勢いの良い、強い枝っていうのをなるべく少し外していって。
柔らかく伸びていく枝っていうのは多少違いがあるので(柔らかい枝)をなるべく残して、枝ぶりをちょっとコントロールして、枝が多すぎるところっていうのを途中から抜いたり、元から抜いちゃったりとかしながら、だんだんこの向こう側が、見えるようになるような感じで木を剪定していく。
基本的には、『柔らかく仕立てていく』 ※動画視聴推奨 03:40〜
あんまり勢いのいい枝を残さないでっていうのが、基本。
色々ちょっと場面場面で、全てがそうだとは言い切れないんだけども、あえて強い枝を残しておくっていう場合もなくはないんですけど。
基本的なこういう剪定としては、あんまり勢いの良いのを残しすぎない。
残さないような形でっていうのが多いかなと思います。
こうやってちょっとスッキリさせていく。
これをひとつの(高い)木の中でやっていく。
「自然の木の形を再現する——それが、僕たちが心がけている剪定です。」
大きい木に関しては、ここまで細かくはおそらくやるシーンというのは少ないと思うんだけども。そういったバランスを取っていくっていう。
それが一応剪定の基本的な仕組みというか、メカニズムかなと思っています。
これをどこでもかんでも切っちゃうと、形は作れても枝をあまり活かせなくなっちゃって、自然な木の形になかなかできないので、なるべく『自然の木の形を再現』できるような、そういう剪定をなるべく心がけているというところですね。
かなり1年で伸びる量が多いんで、毎年やってるような作業ですね。
木の形をキープしつつ、いい枝を残して、樹形が良くなるように整えるって感じです。
次回 【高木剪定】ロープワーク編 へ続く
- 地元・鴻巣市で“手に職”をつけて働きたい方は、今すぐご応募ください。
- 埼玉県で造園の仕事を探している方、未経験からでもスタートできます。
- 未経験の方も一から丁寧に指導。資格取得も会社が支援します。
- 【正社員募集】吉村造園では、一緒に働く仲間を随時募集しています。